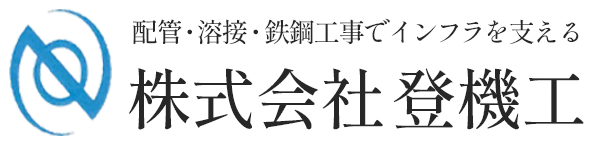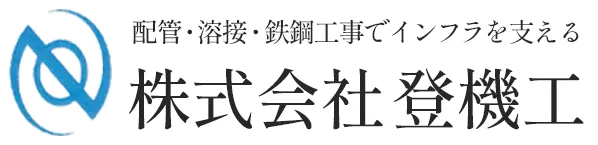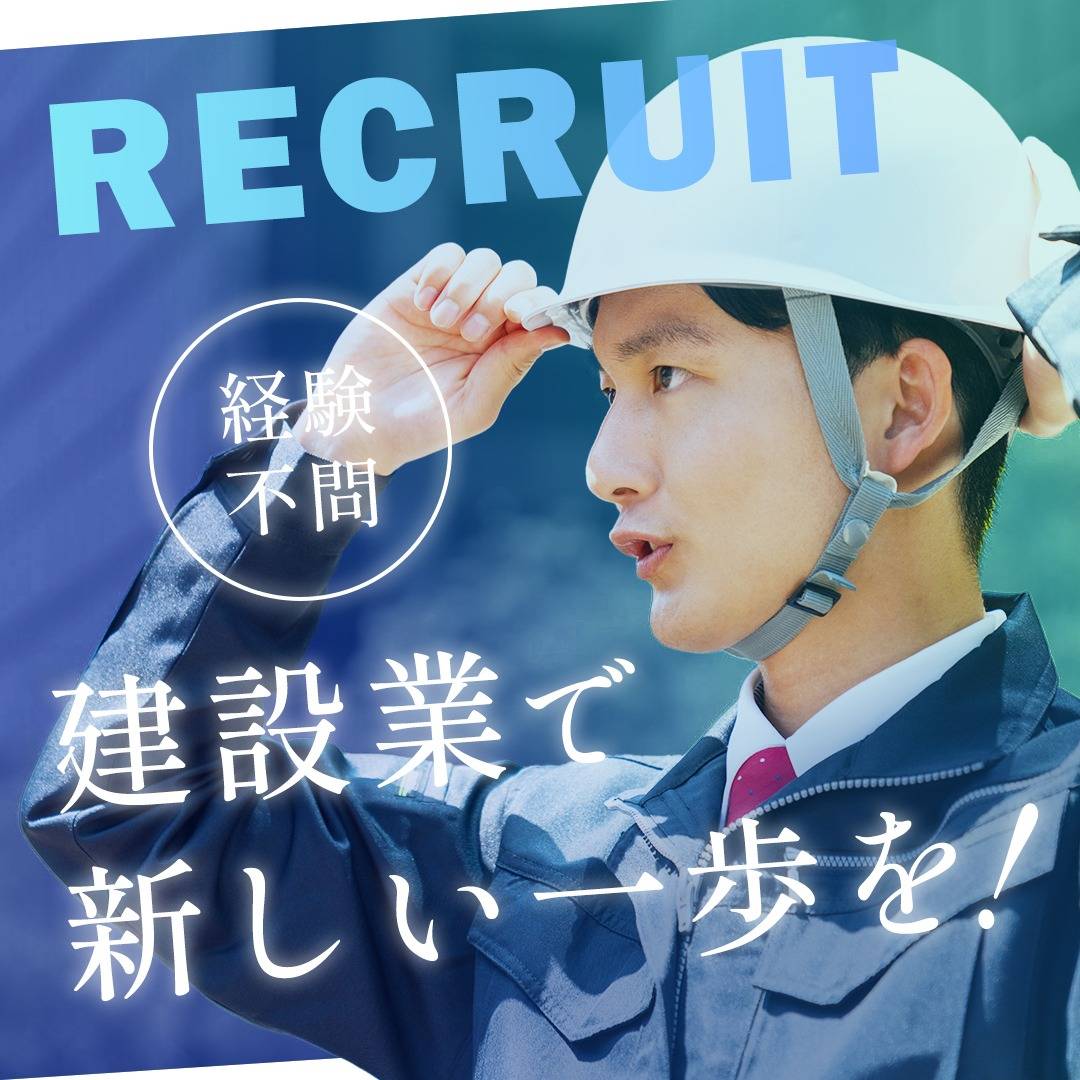建設の環境許可取得で押さえるべき手続きと法令ポイント徹底解説
2025/10/06
建設現場での環境許可取得について、複雑さや見落としがちな法令ポイントに困惑した経験はありませんか?建設業界では、許可の有無が工事計画や公共事業の受注資格に直結し、法令遵守と経営の安定化の両立が課題となっています。しかし、最新の建設関連法規や環境許可の取得手続きには、専門的な知識と実務経験が求められるため、戸惑う場面も多いものです。本記事では、建設分野で押さえておきたい環境許可取得の流れや、重要な法令ポイントを徹底的に解説します。読むことで、現場管理や許可取得の精度が高まり、リスク回避と持続的な事業成長へとつなげる実践的な知識を得られます。
目次
建設の環境許可取得で見落としがちな要点
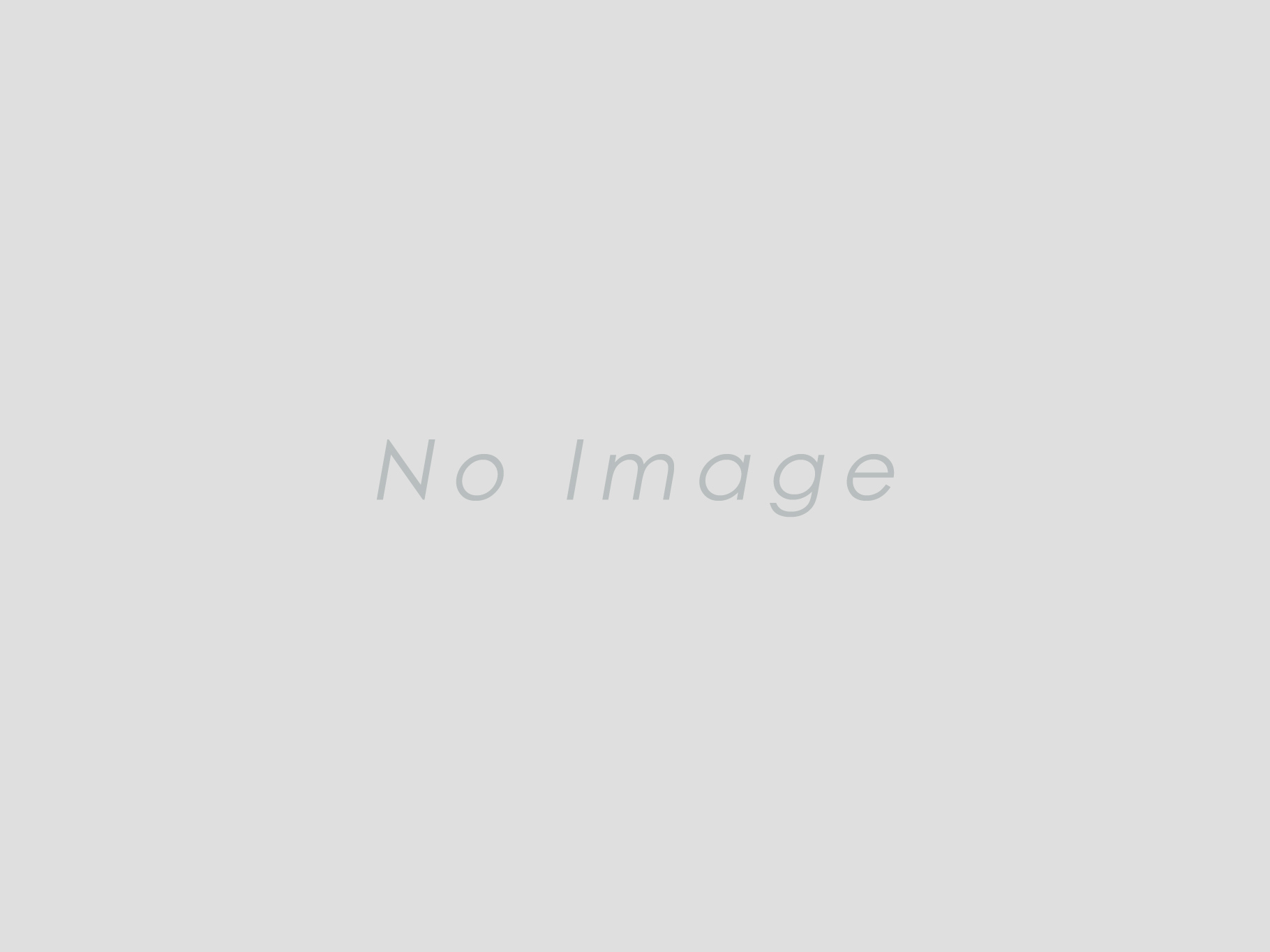
建設現場で環境許可が必要な理由と背景を理解する
建設現場で環境許可が必要なのは、工事が周辺環境に与える影響を最小限に抑えるためです。法令は廃棄物処理や排水管理など多岐にわたり、許可取得は環境汚染防止と安全確保の観点から必須です。例えば、産業廃棄物の適正処理が求められ、違反時は行政処分が科されます。つまり、環境許可は建設事業の持続的運営に不可欠な基盤といえます。
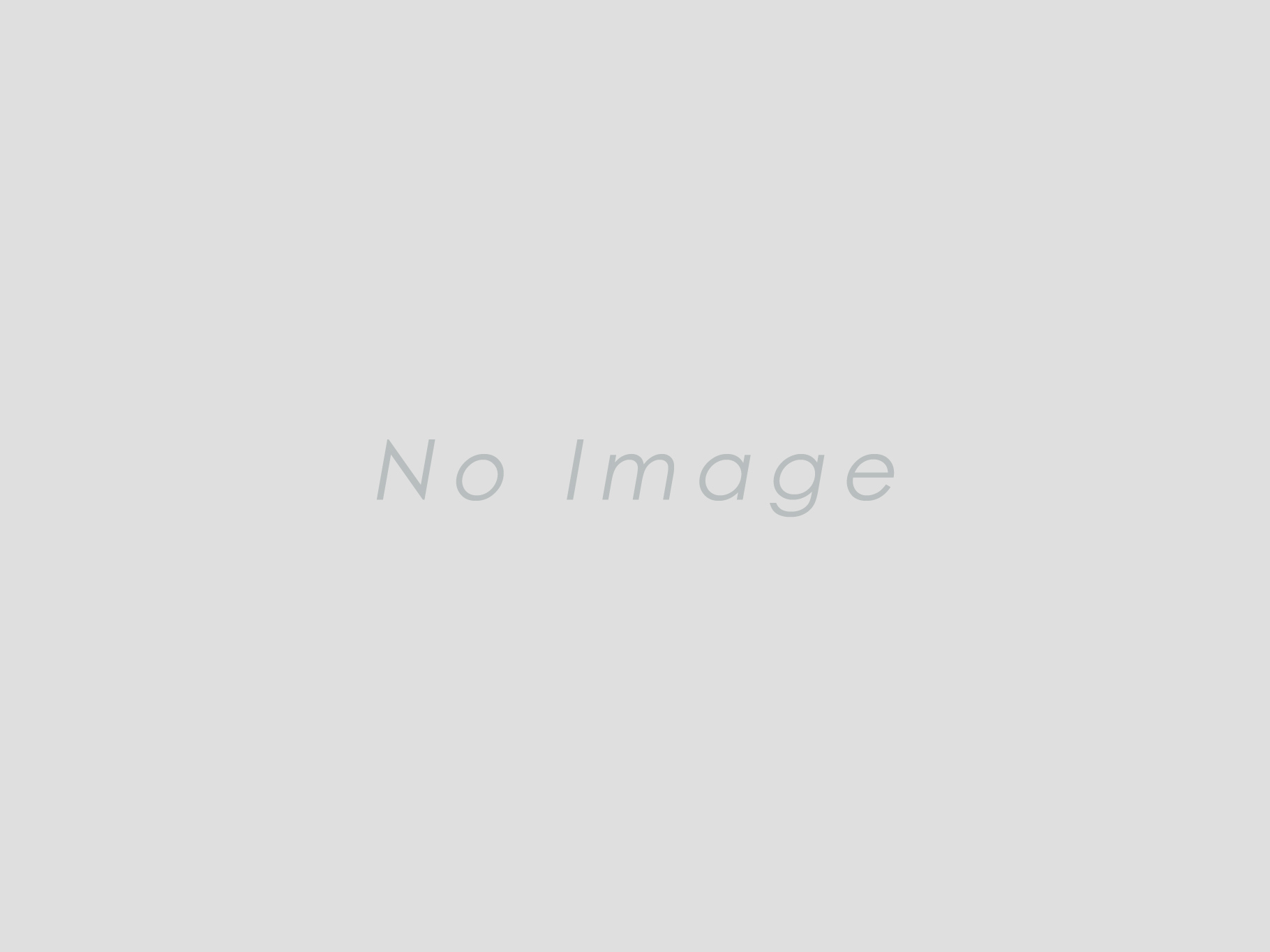
建設の環境許可に関する最新法令のポイント整理
最近の法令改正では、特別管理産業廃棄物の規制強化やマニフェスト制度の厳格化が注目されています。これにより、排出事業者の責任が明確化し、下請け業者との委託関係も厳しく管理されます。具体的には、収集運搬業者の許可確認や適正な保管場所の確保が必須です。これらは違反リスクを減らし、環境保全の信頼性を高めるための重要ポイントです。
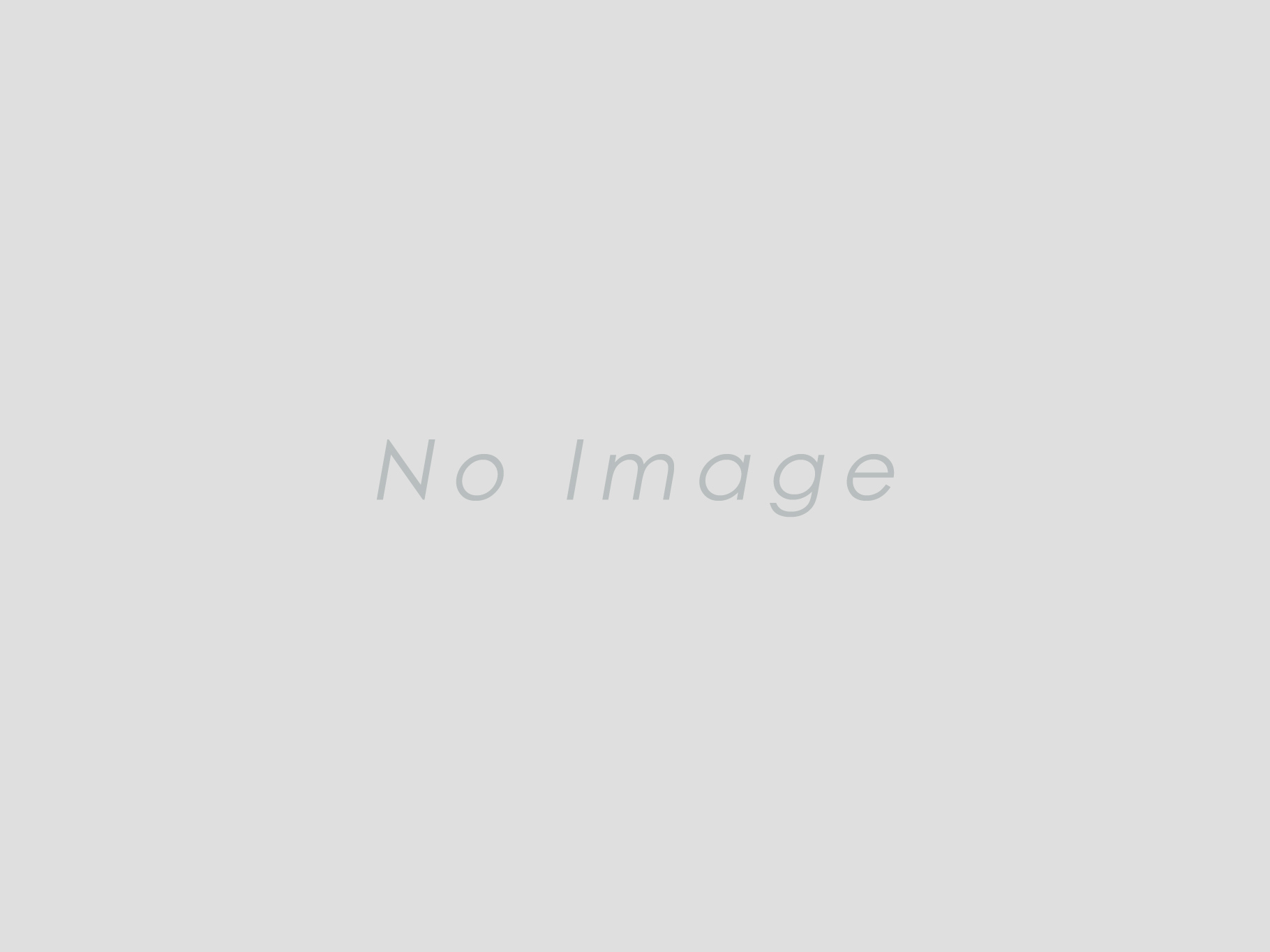
見落としがちな建設環境許可の注意事項を解説
建設環境許可では、産業廃棄物の種類ごとの処理基準や、排出量の把握が見落とされがちです。たとえば、木くずやコンクリート片の扱いは一般廃棄物と異なり、産廃としての適正処理が必要です。さらに、環境影響評価の有無や、騒音・振動規制への対応も忘れてはなりません。これらのポイントを踏まえた継続的な管理が法令遵守の鍵です。
環境法令遵守による建設業の安定経営
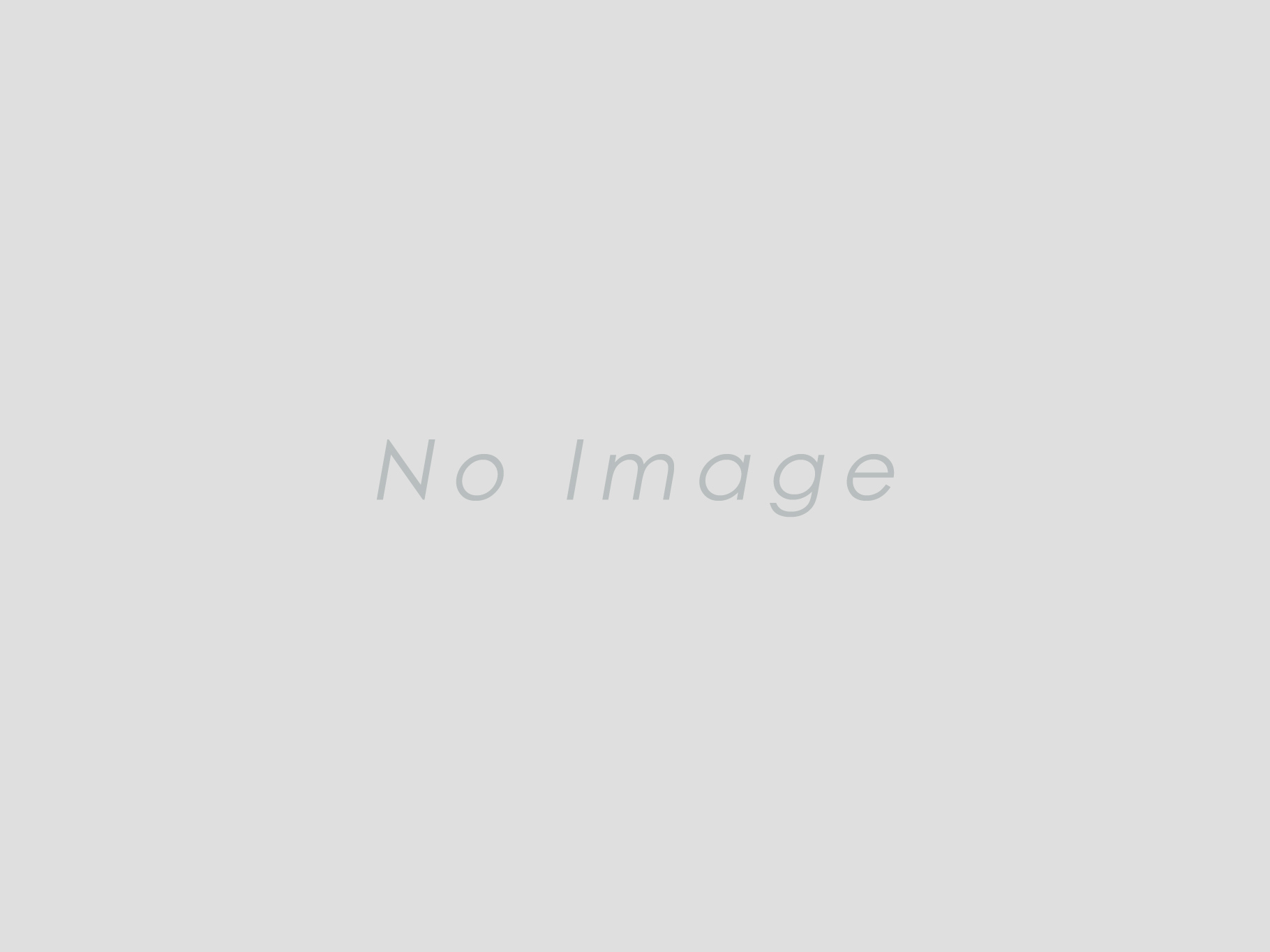
建設現場の環境法令遵守が経営にもたらす影響
建設現場での環境法令遵守は、企業の信頼性向上と経営安定に直結します。法令違反は行政処分や工事停止のリスクを招き、受注機会の損失につながるため、遵守は必須です。例えば、産業廃棄物の適正処理を徹底することで、地域社会からの信頼を確保し、持続可能な事業運営が可能になります。したがって、環境法令遵守は経営戦略の重要な柱となるのです。
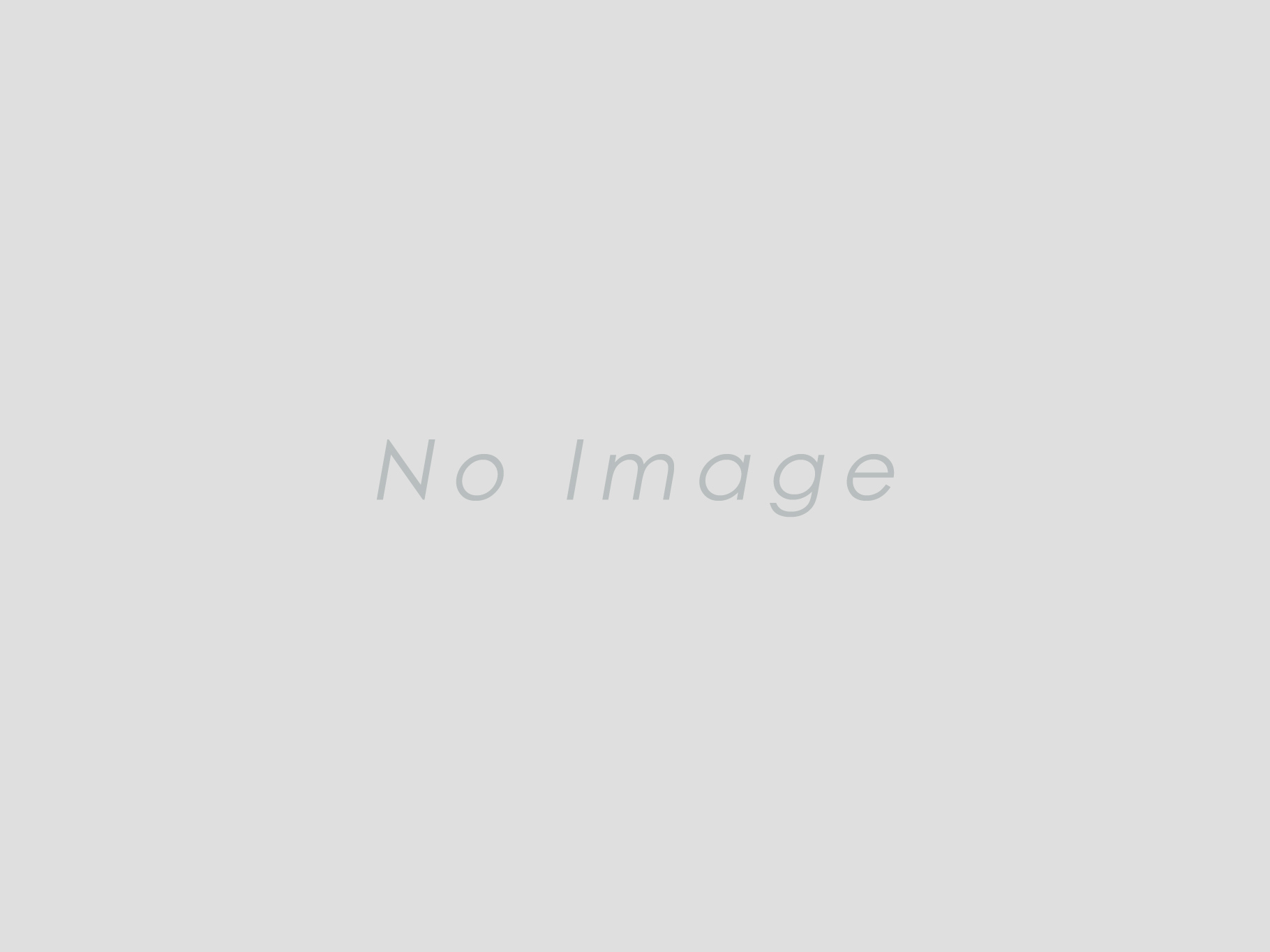
安定経営のための建設法令管理体制の整え方
安定経営には法令管理体制の整備が不可欠です。具体的には、環境許可申請の担当者を明確化し、法改正情報の定期的な収集と共有を行うことが重要です。例えば、社内規定に基づくチェックリストを作成し、申請漏れや違反を未然に防止する体制を構築します。こうした組織的な管理が、法令違反リスクの低減と円滑な許可取得につながります。
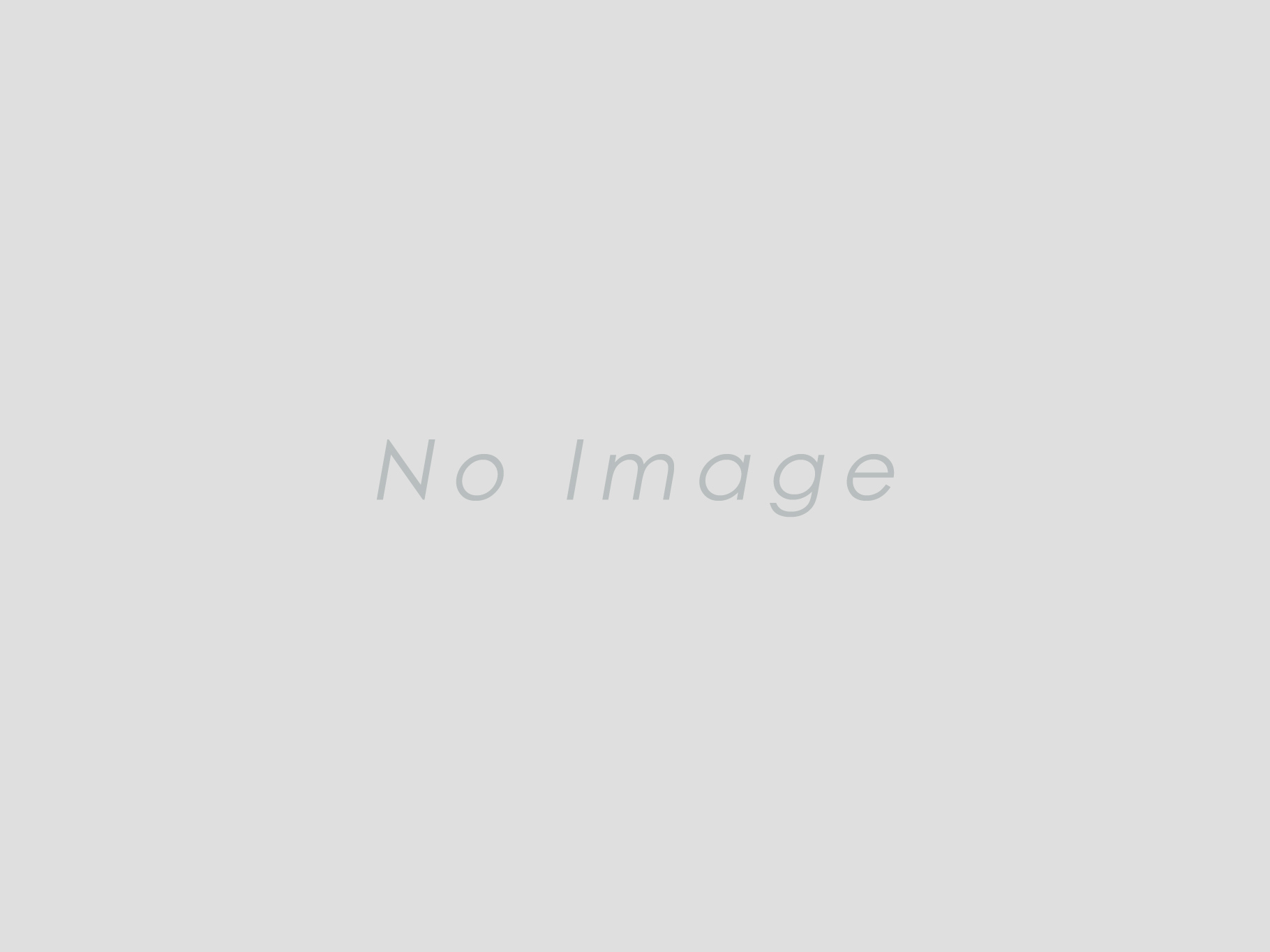
建設許可違反を防ぐリスクマネジメントの重要性
建設許可違反防止にはリスクマネジメントの強化が欠かせません。具体的には、許可内容の遵守状況を定期的に監査し、違反の芽を早期に発見する仕組みを導入します。例えば、産業廃棄物の処理委託先の適正性確認やマニフェスト管理の徹底が挙げられます。これにより、違反による罰則回避と共に、企業の信用維持を図ることが可能です。
工事現場の環境許可を確実に得るコツ
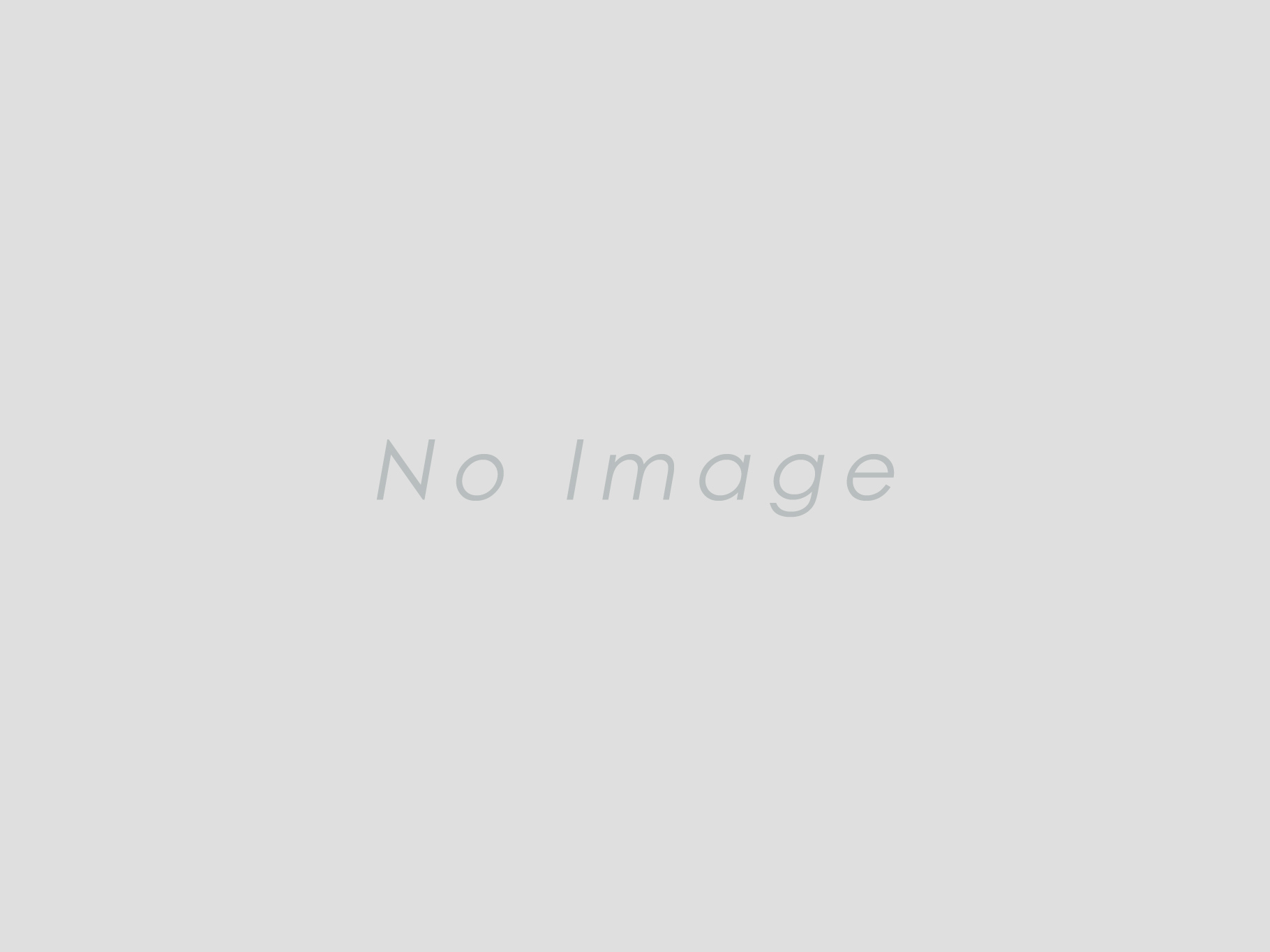
建設工事で環境許可申請を成功させる準備方法
建設工事で環境許可申請を成功させるためには、まず事前準備が欠かせません。具体的には、対象工事の規模や内容を正確に把握し、関連する環境法令を確認することが重要です。例えば、産業廃棄物の排出量や種類を詳細に調査し、適切な処理計画を立てることで申請の精度が上がります。この準備段階を丁寧に行うことで、後の手続きがスムーズに進み、法令遵守を確実にできます。
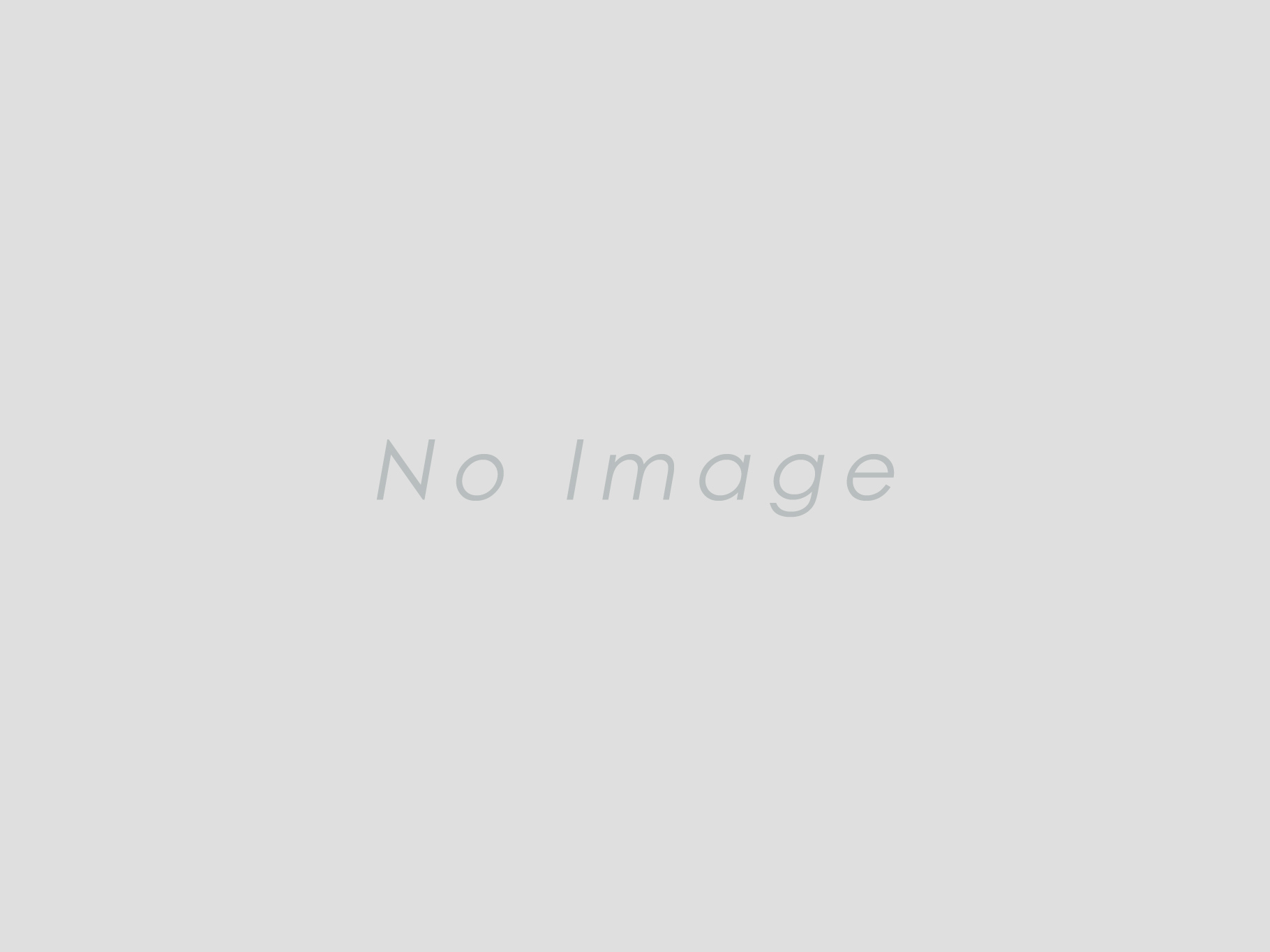
現場ごとに異なる建設許可要件の整理と対策
建設現場ごとに環境許可の要件は異なるため、要件整理と対策が必要です。例えば、都市部の工事では大気汚染防止法の遵守が厳しく求められ、一方で郊外では水質保全の観点が重視されます。これらの要件を現場の特性に合わせて整理し、適切な環境対策を講じることが成功の鍵です。具体的には、騒音対策や廃棄物管理計画を現場条件に応じて作成し、関係機関と連携を図ることが推奨されます。
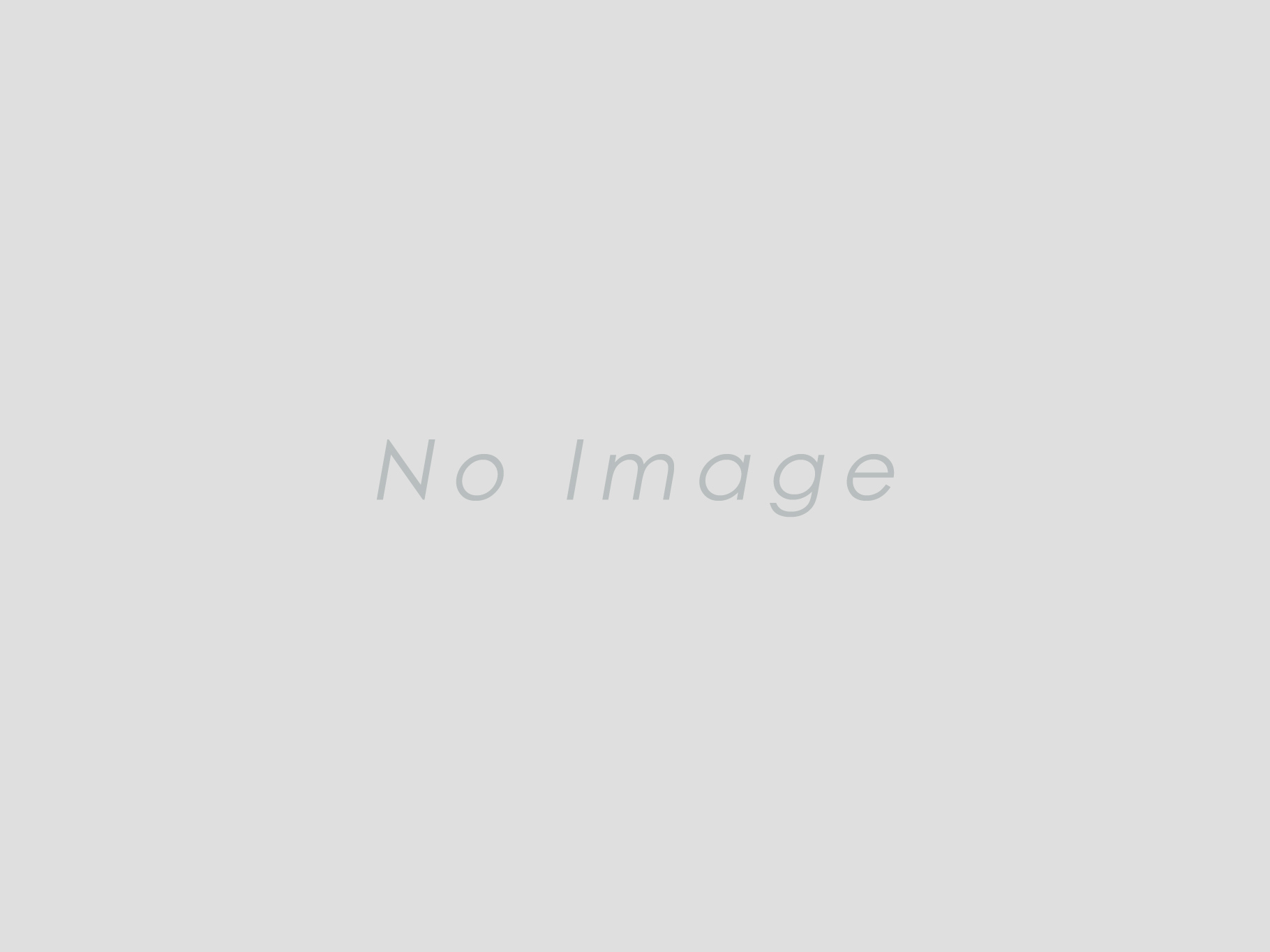
建設現場の書類作成や申請手続きの流れを解説
建設現場での環境許可申請には、書類作成と申請手続きの明確な流れがあります。まず、必要書類のチェックリストを作成し、工事計画書や環境影響評価書を準備します。次に、所管行政庁への提出前に社内での確認を徹底し、不備を防ぎます。申請後は、行政からの問い合わせに迅速に対応し、補足資料の提出も速やかに行うことが重要です。この流れを踏むことで申請の合格率が向上します。
建設で求められる産業廃棄物処理の実務知識
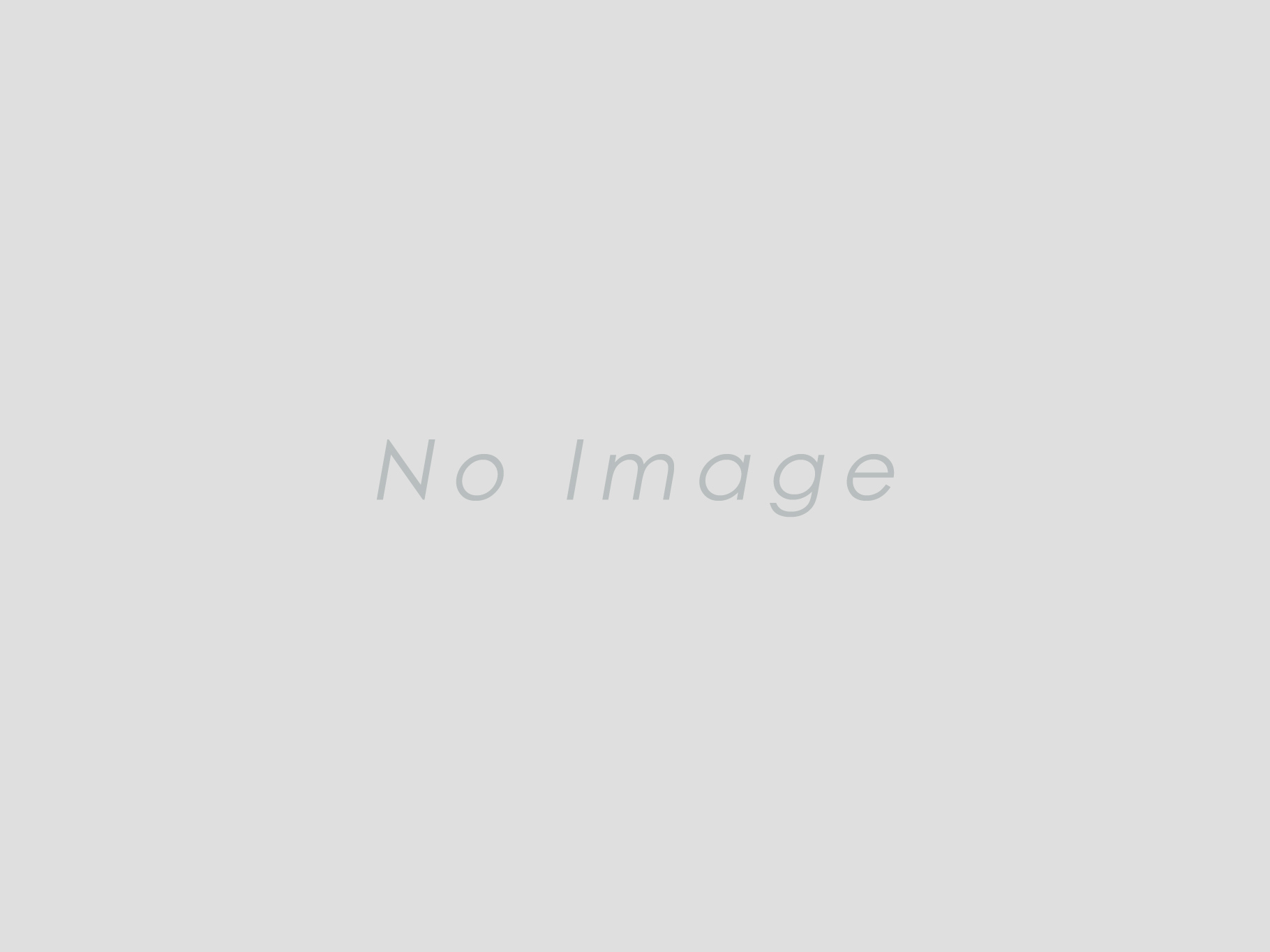
建設現場で必要な産業廃棄物処理の基本と流れ
建設現場では、産業廃棄物の適切な処理が不可欠です。まず、廃棄物の種類を把握し、分別を徹底することが基本です。次に、排出事業者として産業廃棄物処理の責任を明確にし、適正な処理業者へ委託します。具体的には、廃棄物の収集運搬、処分までの各段階で法令を遵守する必要があります。適正管理体制の構築により、環境負荷を軽減し法令違反リスクを回避できるため、現場での持続可能な運営が可能となります。
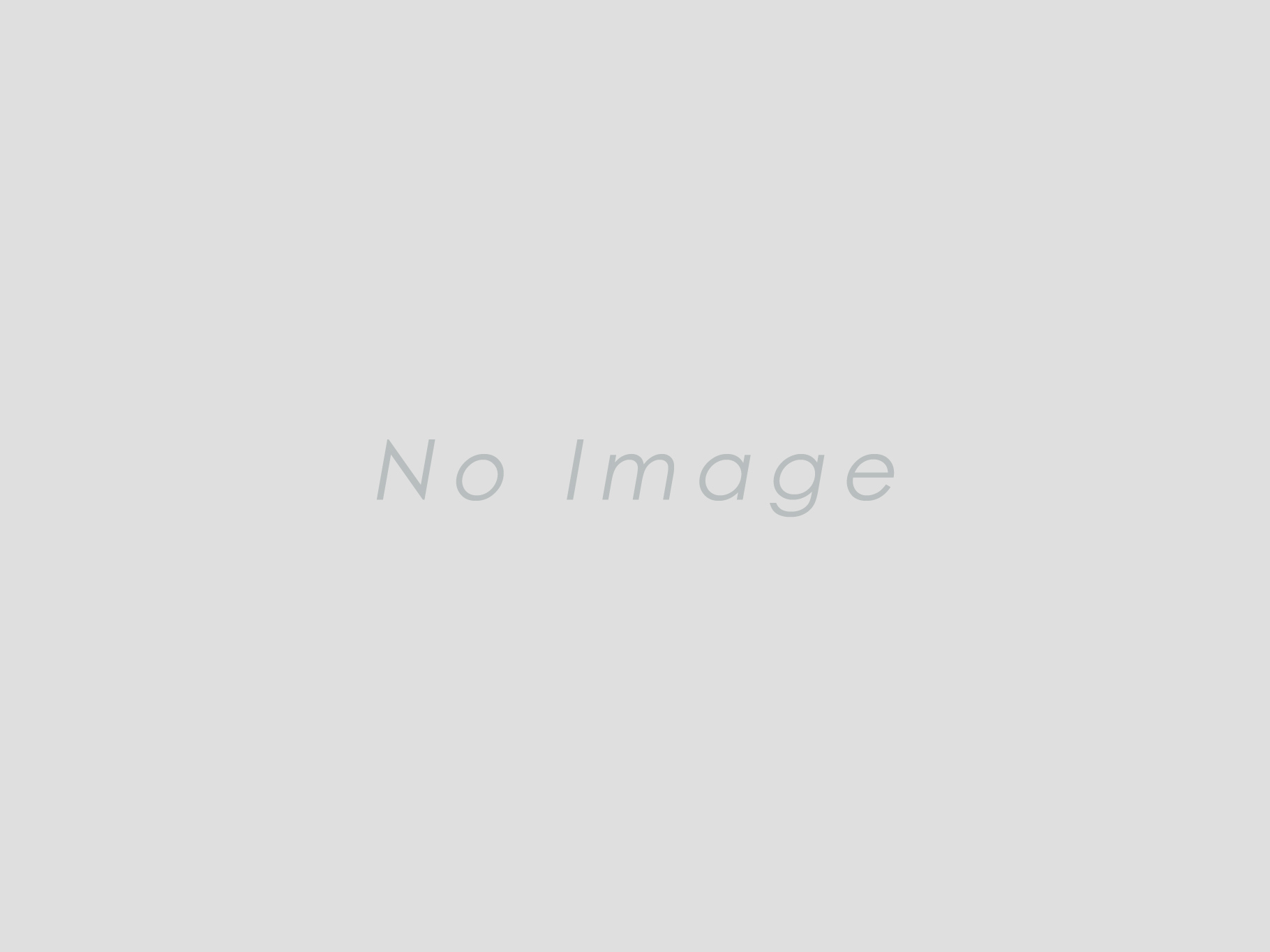
建設業者が守るべき廃棄物処理ガイドライン要点
建設業者は、産業廃棄物処理に関するガイドラインを遵守することが求められます。これには、廃棄物の適正な分別、保管基準の厳守、マニフェストの利用が含まれます。特に、マニフェストは排出から処分までの追跡を可能にし、法令遵守の証明となります。具体的には、廃棄物の種類ごとに処理方法を定め、定期的な内部監査や研修を実施することで、違反リスクを低減し、現場の環境保全を強化できます。
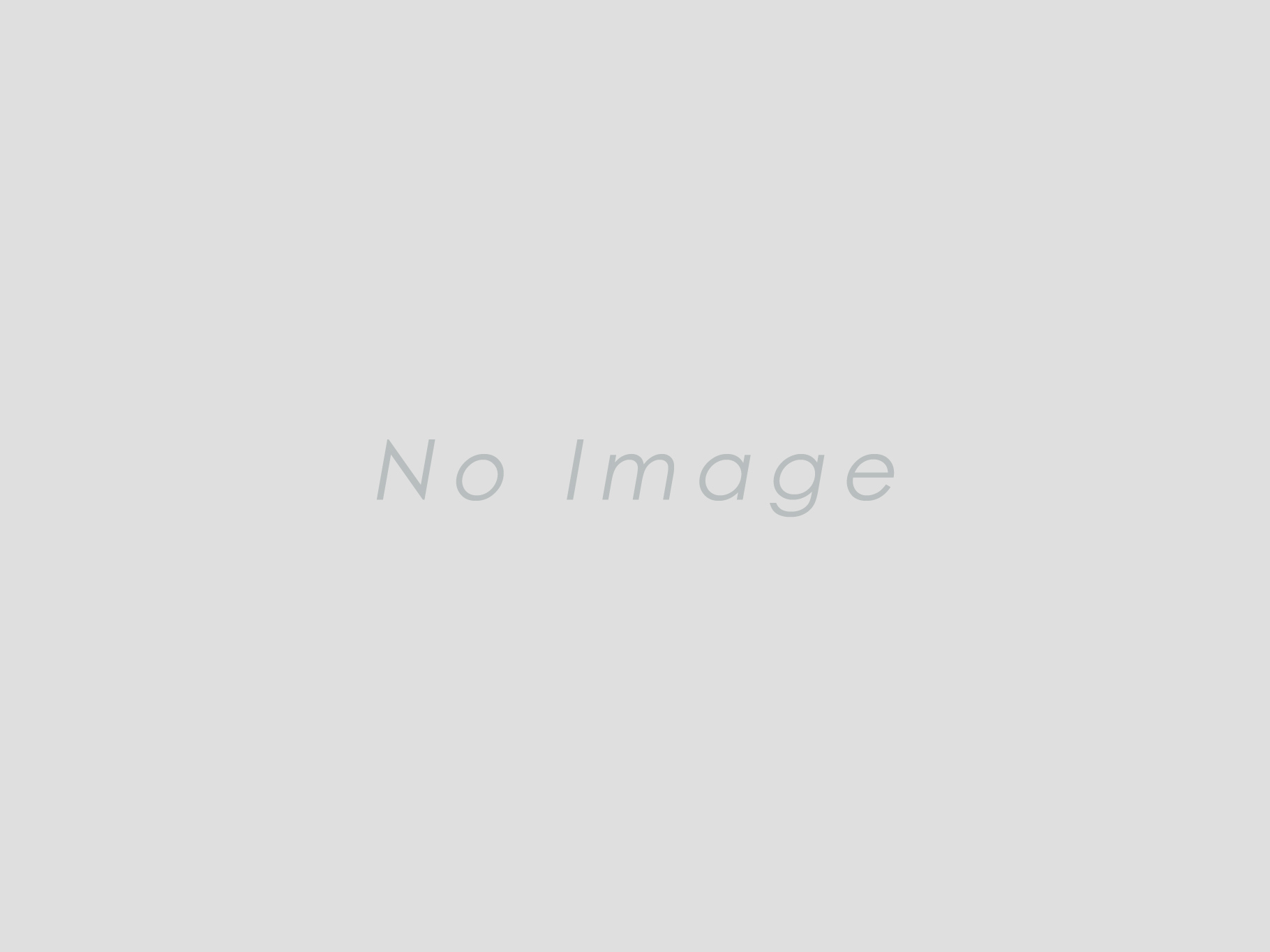
建設廃棄物の適正管理とマニフェスト活用方法
建設廃棄物の適正管理には、マニフェスト制度の活用が鍵となります。マニフェストは、廃棄物の排出、収集運搬、処理の各段階を記録・管理し、情報の透明性を確保します。具体的には、マニフェストの記入漏れや誤記を防ぐため、専用のチェックリストを導入し、関係者間で共有することが重要です。これにより、法令違反の防止と環境負荷の軽減が実現し、建設現場の信頼性向上につながります。
許可不要な建設工事の判断基準とは何か
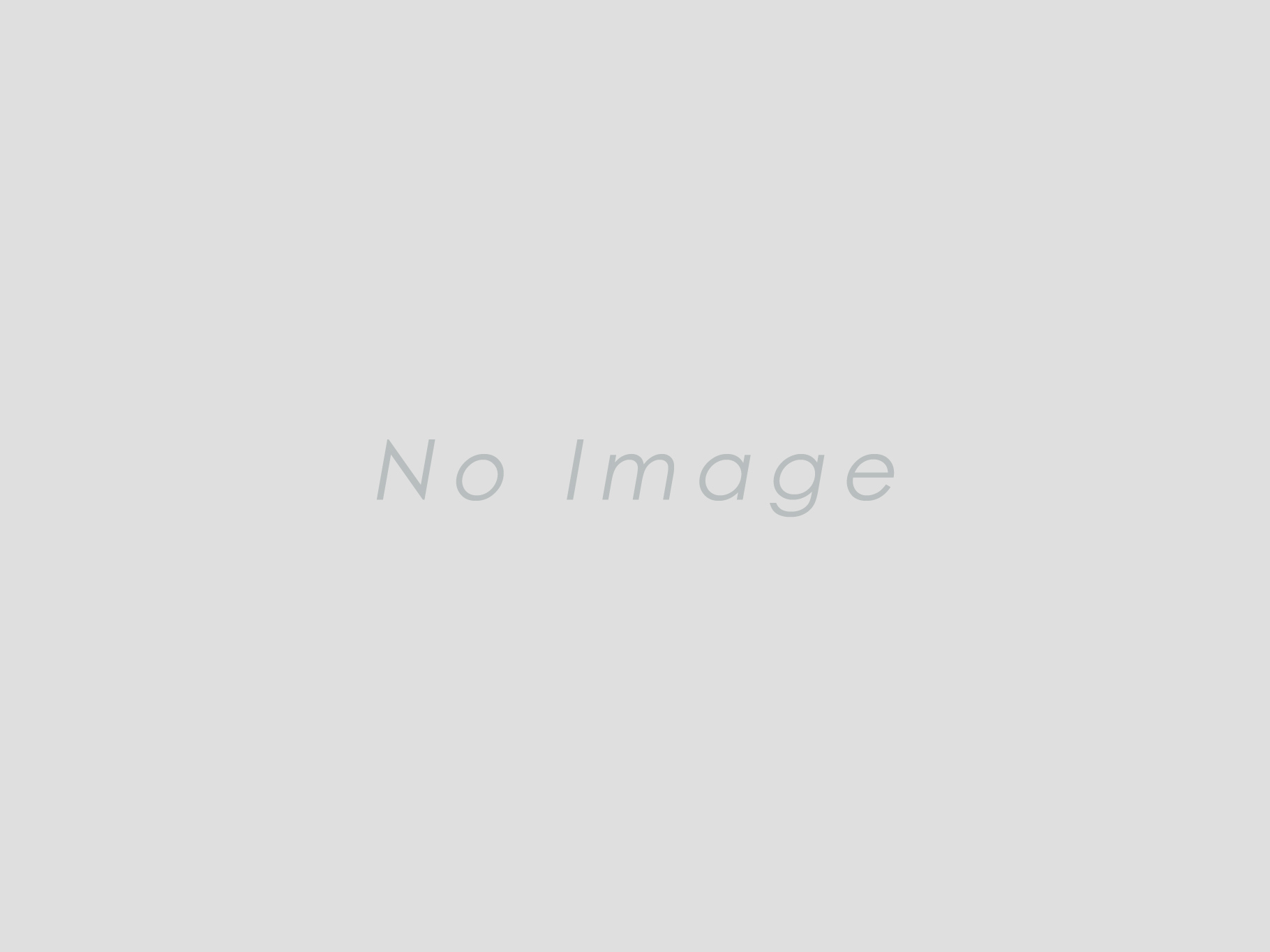
建設業で許可が不要な工事の具体例と根拠整理
建設業において許可が不要な工事には、一定の規模や内容が限定されたものが含まれます。例えば、小規模な補修や修繕工事は許可不要とされることが多く、建設業法第3条の規定に基づき明確に根拠づけられています。これにより、事業者は許可申請の手間を省きつつ法令遵守を図れます。したがって、具体的な工事内容の把握と法律の適用範囲の理解が不可欠です。
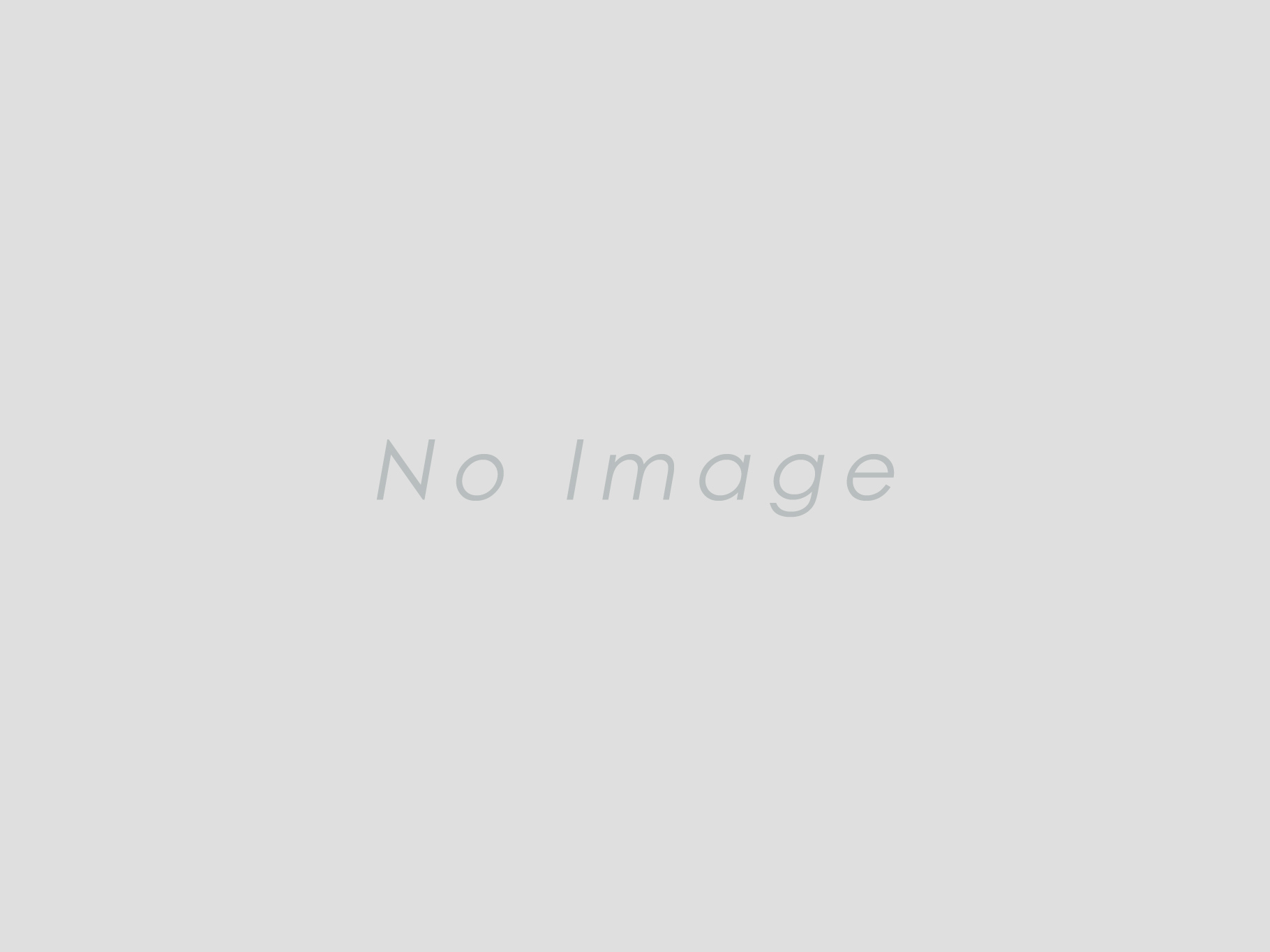
許可不要工事と必要工事の違いを見極める方法
許可不要工事と必要工事の違いは、工事の規模や内容、使用資材の種類などで判別されます。具体的には、施工面積や工事金額の基準を法令で定めているため、これらの数値と照合し判断します。例えば、一定の面積以下の工事は許可不要ですが、それを超える場合は許可が必須です。この見極めにより、適切な手続きを行い法令違反を防止できます。
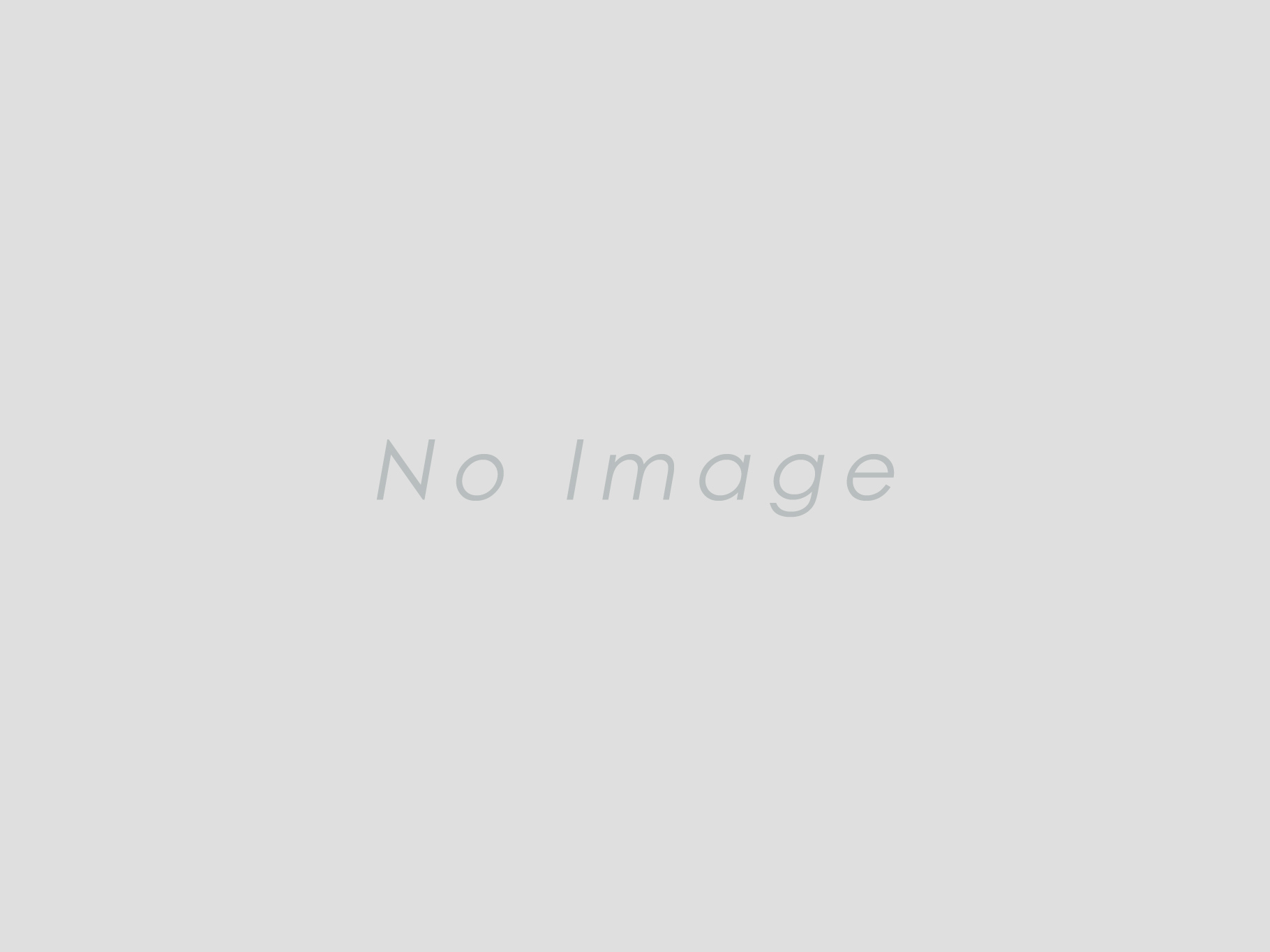
建設現場で知っておきたい許可不要の条件解説
建設現場での許可不要条件は、工事の対象物の種類や作業範囲、使用資材の性質に左右されます。具体的には、簡易な修繕や軽微な補修工事、自己使用のための小規模な建築作業が該当します。これらは建設業法や環境関連法令で例示されており、現場管理者はこれらの条件を正確に把握し、不要な許可申請を省くことで作業効率を高められます。
建設業許可取得手続きの最新動向を解説
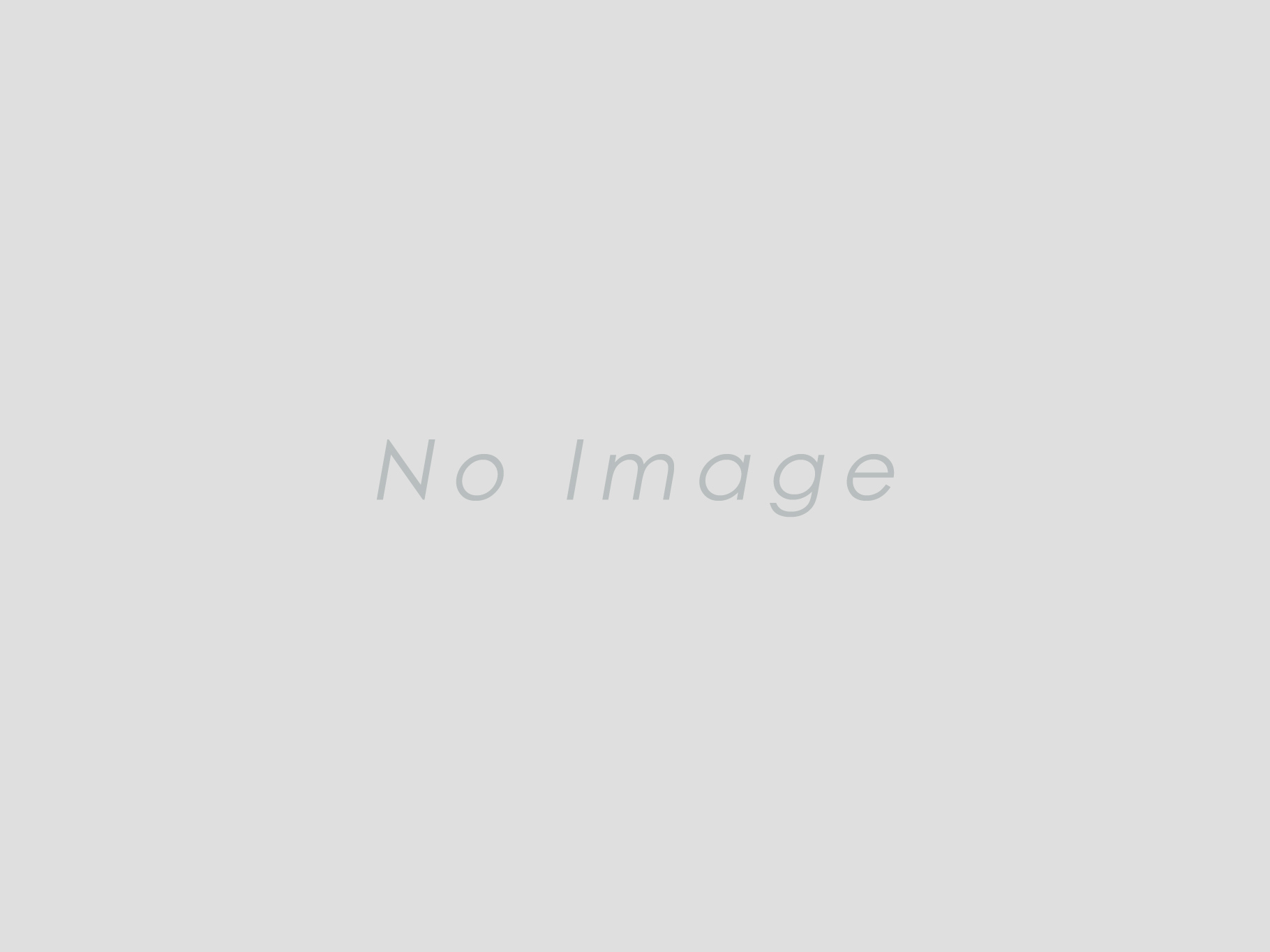
建設業許可の種類と取得手続きの全体像を整理
建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があり、それぞれの取得手続きは異なります。許可の種類は受注可能な工事規模や下請け関係に影響するため、事業計画に応じて適切な許可を選択することが重要です。例えば、元請として大規模工事を請け負う場合は特定建設業許可が必要となり、これにより工事の安定した受注が可能になります。全体像を把握し、必要な手続きを順序立てて進めることが許可取得成功の鍵となります。
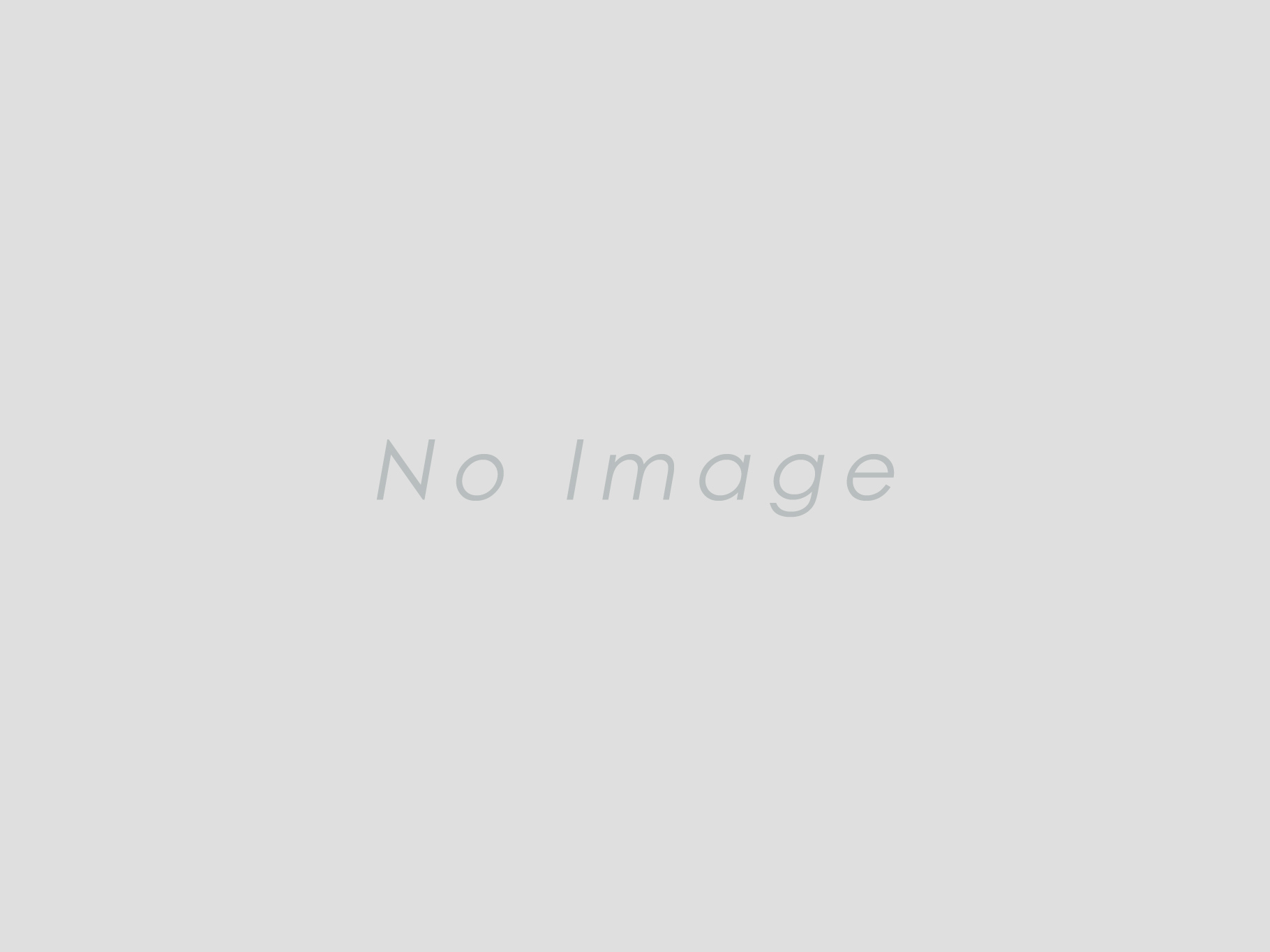
建設許可申請の流れと注意点を最新情報で解説
建設許可申請は申請書類の準備、審査、許可証の交付という流れで進みます。最新の法令改正により、電子申請の利用が推奨されており、申請ミスを減らすためにも公式サイトのガイドラインを熟読することが必須です。注意点としては、申請内容に虚偽がないこと、必要書類を漏れなく揃えることが挙げられ、これにより審査期間の短縮と許可取得の確実性が高まります。実務経験者のサポートを受けることも成功のポイントです。
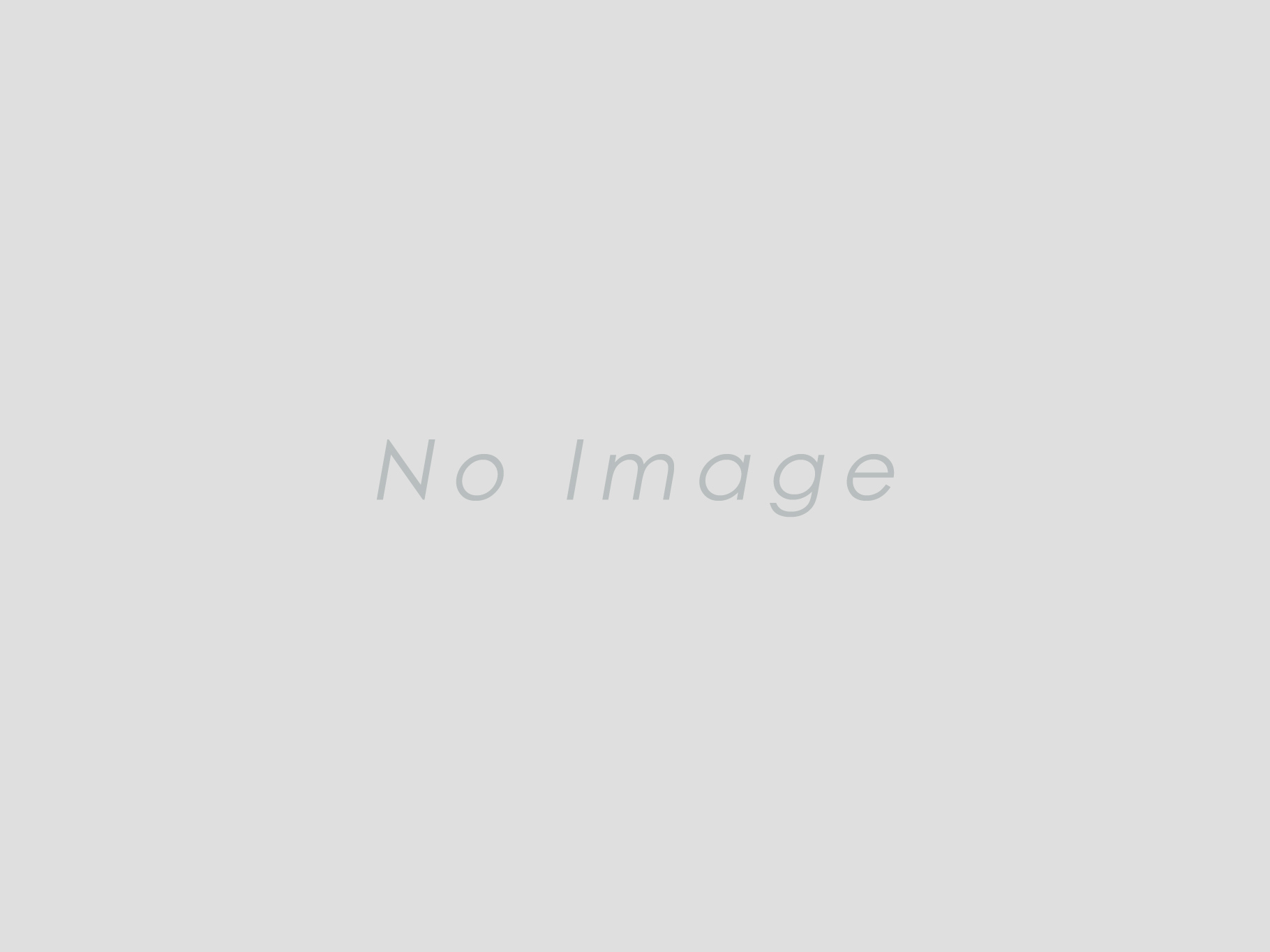
申請書類作成で押さえるべき建設の実務ポイント
申請書類作成では、過去の工事実績や経営状況を正確に反映することが求められます。具体的には、工事内容の詳細な記載、建設業法に基づく必要書類の添付、そして環境関連の許可状況の明示が重要です。実務上は、書類の整合性を保つために複数回のチェックと専門家の確認を行うことが推奨されます。これにより、申請の不備を防ぎ、審査をスムーズに進めることが可能となります。